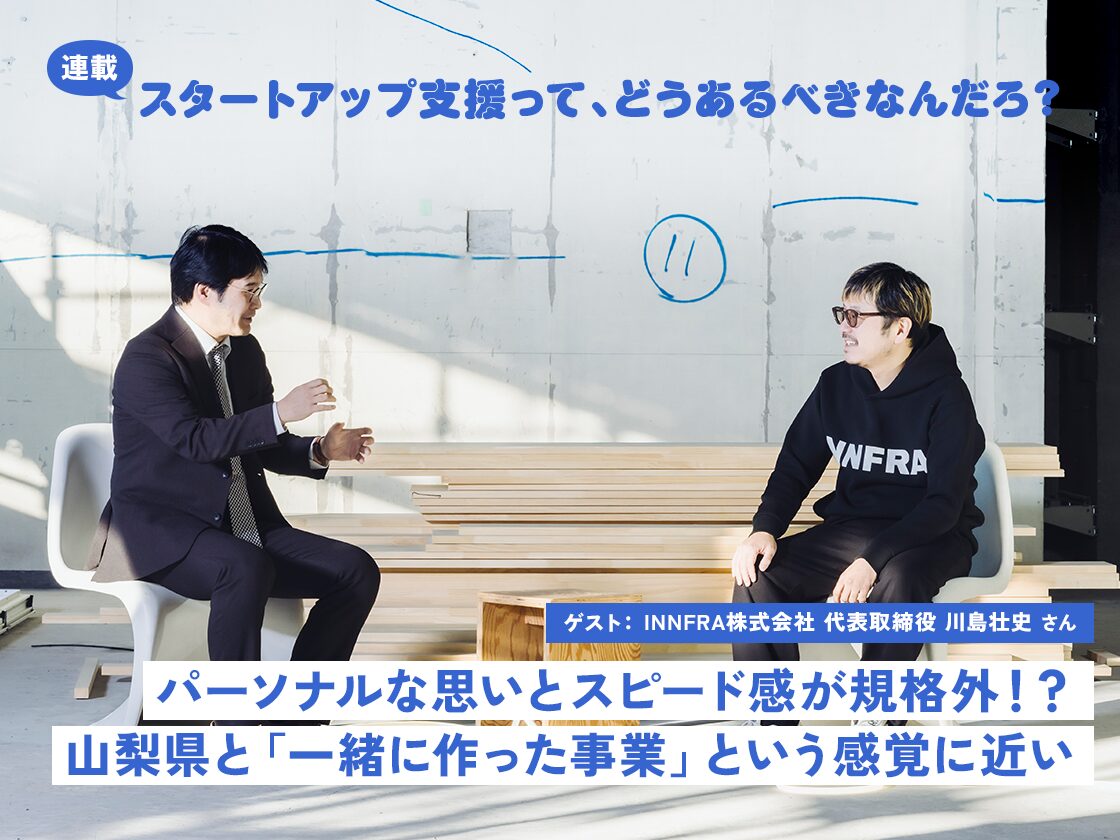
山梨県庁にスタートアップ・経営支援課が誕生して、まもなく2年。「汗をかく行政」を合言葉に、誘致から資金調達、起業支援や成長加速サポートまで、各領域を横断して奔走する様々な支援事業を展開しています。
2025年秋には、県下発のスタートアップ支援拠点が誕生予定。全国にさまざまな支援拠点が生まれる中、山梨の支援拠点はどんな場所であるべきなのでしょうか。
連載「スタートアップ支援って、どうあるべきなんだろ?」は、この問いのヒントを探る企画。山梨県スタートアップ・経営支援課が、毎回ゲストをお招きし、建設途中の工事現場で「あーでもない、こーでもない」と対話を重ねていきます。
今回は、スタートアップ経営支援課が動き出すよりも以前から(令和4年度「TRY!YAMANASHI!! 実証実験サポート事業」に採択)山梨県北杜市にラボを構え、インフラのイノベーションによる社会課題解決に取り組むINNFRA・川島壮史代表が登場。山梨県の支援を受けたスタートアップの立場から「実際どうだったか?」を語ってもらいました。
東京大学大学院理学系研究科修了後、インフラ業界の経営コンサルティング、エネルギー関連の新規事業開発、スタートアップの経営などに従事。2022年3月より山梨県北杜市でインフラの実証プロジェクトを立ち上げた後、2023年10月にINNFRA株式会社を設立、代表に就任。
東京都 あきる野市出身。徴税や農政部、県土整備部など、さまざまな部署を経験後、2023年に新設されたスタートアップ・経営支援課へ。「汗かく行政」をスローガンに掲げ、スタートアップ企業への伴走支援に取り組んでいる。
イノベーションの力でインフラを変えていく
いきなりなんですが、実は、INNFRAさんが山梨に入られたタイミングでは僕らスタートアップ・経営支援課はまだ立ち上がっていなかったんです。
スタートアップ・経営支援課が立ち上がったのが、僕らが「TRY!YAMANASHI!! 実証実験サポート事業(令和4年)」に採択されたあとなんですよね。
そうそう、令和5年4月。その時にご挨拶させていただいて、ものすごく魅力的なスタートアップだと思って。
ありがとうございます。僕らは「イノベーションの力でインフラを変えていく」を合言葉に、インフラが直面している社会課題を解決していくことをテーマにしています。中でもエネルギーと水。暮らす上で必要最低限となる“ライフラインのインフラ”にフォーカスして技術開発を行っています。
どうして”インフラ”をテーマにされたのですか?
背景としては大きく2つあります。ひとつは人口減少の社会課題。地方を中心に人口減少が進むと自治体収入が減り、インフラを維持するのが難しくなると予測されています。インフラが廃れてしまっては、さらに人の暮らしは困難になる……。インフラを刷新することができれば、この負のスパイラルを食い止めることができると考えたんです。
もうひとつが自然災害に対するレジリエンス強化のため。地震や水害によって大規模な被害が発生すると、避難生活すらままならないというのを我々は目の当たりにしてきたわけで。そこに対して、僕らの技術で貢献できる可能性を感じています。
北杜には「呼ばれてきた」気がする
その技術開発の場として、北杜市に完全オフグリッド(※)環境での生活実証施設「オフグリッド・リビングラボ八ヶ岳」がある。そもそもなんで山梨だったんですか?
※電力、ガス、水道などの従来のライフライン(インフラ)に依存せず、自給自足により独立して確保できるよう設計された建物やその生活様式のこと

きっかけは本当に偶然でした。オフグリッドがこれから重要なテーマになるんじゃないかとなったとき、技術的に可能だということはすぐに分かったのですが、それを本当に実装して閉鎖空間で暮らしている人や実験は見当らない。
自らオフグリッドの環境に身を投じて暮らしている”変わり者”はいなかったわけですね。
インフラを変えていくというときに、ちゃんと実体験やフィールドワークを通じた検証をともなわず、いきなり技術だけ実装するというのはアレじゃないですか。安心安全がインフラの基本なのに。だから、そういった実験が必要なんじゃないかと思い、世の中にないのであれば作ってしまえということでラボの立ち上げに向けて動き出しました。

とはいえそんな実験が可能な、自由な土地というのはなかなか見つからないだろうと思っていたんです。けれど、たまたま前職のつながりで、あの広大な土地を借りていた企業さんと出会い「余っている土地でラボを作らせてください」とお願いしたらすんなりOKをいただけて。
それはよかった。
だから、ちょっと申し訳ないんですけれど、「山梨を選んだ」というわけではないのです。
いやいや、いいんですよ。ご縁があったことが素晴らしい。
ただ、今になって感じているのが、必然性があったのだろうということ。とくに北杜市エリアは移住者が多かったり、アーティストや有名な建築家の方なども活動されていたり、僕らがやっていることを面白がってくれる方も多かった。北杜エリアを中心に、山梨で色々な方と接する中で「これはやはり求められているんだな」とか「面白い未来が描けそうだ」とか、手応えを感じられました。自信を得られたというか、ものごとを前に進めるための勇気みたいなものをもらえたと感じています。
そこが川島さんの強いところですよね。ビジネスプランがパワポの資料だけじゃなく、「本当にやっていますよ」と示せてしまうんだから。多くのスタートアップと一線を画しているポイントだと思います。
メディアツアーで大バズり。
実際に我々(山梨県)の支援ってどうでしたか?
僕らは冒頭にもお話しした「TRY!YAMANASHI!! 実証実験サポート事業」に採択いただいて半年間の伴走期間をいただきました。そこで協力をお願いしたのは大きくは3つ。1つは地元の企業さんとのネットワーキングやマッチング。これは実験の先を見据えていく上で、または意見交換をしていく上で必要で、紹介いただけたらありがたいなと。もう1つはインフラという事業の特徴でもある制度対応のサポート。保健所や規制官庁とのディスカッションや調整などのヘルプもお願いしました。そして最後の1つがプロモーションの支援。とくにこのプロモーション支援がすごくて、こんなことまでできるんだ!と感動させられましたね。
我々(山梨県)と共催でメディアツアーを開催しましたね。INNFRAさんの「オフグリッド・リビングラボ八ヶ岳」にテレビや雑誌などを誘致して、完全オフグリッドの生活実証を実際に体感いただくという内容で。
ただ「山梨県」という名前を貸すだけじゃなく、メディアの誘致や当日の運営、記者対応、全部一緒にやってくださったんです。
記者クラブへの投げ込みにはじまり、個人的なネットワークを駆使して県内メディアだけでなく、県外のメディアにもつないでいただいて。あそこまでハンズオンで一緒に汗をかいてくれるというのは、想像を絶する経験でした。1日のツアーの中で、オンラインを含めると約20〜30のメディアにご参加いただきました。
テレビ、新聞、雑誌のすべて網羅して、山梨県内では即日夕方のニュースで放映されていましたね。
僕らは今「無印良品」さんと共同開発プロジェクトを行なっていますが、間違いなくあのプロモーションがきっかけだったなと。

だから、支援というより“一緒に作った事業”という感覚に近いんです。僕らの取り組み、僕らの会社を本当に大事に思ってくれていますし、皆さんに足を向けて寝られないですよ。笑
あはは。僕は当時メインの担当ではなかったんですけど、みんな川島さんの取り組みに惚れていますから。
県とか県庁の枠組みというより、個人のパーソナルな思いで裁量を持って動いてもらっているイメージがあって、そこが印象深くのこっています。“思い先行”で動いてくれる点が、行政の在り方として意外であり、僕らは嬉しかったです。
地方には、解決しなきゃいけない課題がある
「たまたま」山梨に来たという言い方をしましたけれど、僕らのような社会課題解決型のスタートアップは地方から始めるべきだと最近強く思ってて。
ほう。それはなぜですか?
解決しなきゃいけない社会課題がまさに現場にあるからです。「課題がある」ということは、僕らスタートアップからしたら「マーケットがある」ということと同義で、チャンスそのものですから。東京でやっていたら、課題に対してこれだけの解像度で、これだけ行政や関係機関とのコミュニケーションを重ねて実証実験まで……というのはなかなか難しい。
山梨で、県庁と一緒に活動していなかったらINNFRAは今とカタチが違いましたかね?
うーん、想像できないですね(笑)。共同開発のようなかたちで企業さんと事業をご一緒するというところまではやれていたのかなと思います。けれど、ここまでいろんな可能性に気づくことはできなかったと思う。僕らだけでアイデアを出して探索するというのには限界がありますから、ご一緒してなかったらまだアイデアを掘っている段階にいたと思います。
スピード感がまったく違う、と。
これほどまですべてにスピード感を持ってやってこられたのは、山梨ならではの環境に合わせて、山梨ならではの課題に向き合ってきたからこそ。つまり、地域の課題ドリブンで仕掛け続けられたからだと思っています。そこに地域とのネットワークのハブとなる行政の支援があるとないのとでは、仕掛けのスピードや幅の広がりが圧倒的に違うと思いますね。
プロセスに対する自負
こう話すとなんか、「最初から狙って全部うまくいきました!」みたいに聞こえるかもしれないですけれど、やっぱり過程はもう大変なことがいっぱいありました。
あははは。僕は北杜市のラボに行って、水の匂いに感動しました。排水を再利用して浄化するシステムを導入しているということでしたが、普通の水道水とまったく変わらなくて。
ちゃんと苦労して、出来上がってからをお見せしているから、そう思っていただけているのだと思います。
自ら身を投じて、直に体験して作り上げた技術ということですね。
ええもう、その通り。だから実験を始めたばかりの頃とはシステムも全然違っていますし、とにかくいっぱい失敗しているんです。「これ全然処理できないどうしよう…」とか、「もうちょっとこうしないとダメだな」というのを繰り返してきました。
自負するとすれば、他社のラボでやってもらうとかじゃなく、自分で実験したことですよね。自分でシャワーを浴びながら、その水をどうやって処理するのか、これで足りるのか、こういうことをしないとダメ、これはやばい…、という過程を経てここまできた。これは、本当にやってよかった。一つの成功体験になっています。
僕らもそれを山梨でやっていただけてよかった(笑)
もうひとつ、やっぱり北杜でよかったというのがあって、僕は栃木県出身で大学からは東京。アウトドアをやるタイプでもないので、都市部での生活ばかり。地元に愛着はあるけれど、生活となれば東京、マンション…、みたいな感じだったんです。でも今回、図らずも北杜市に暮らすことになって感じたのは「なんて豊かな生活をさせてもらっているんだろう」ということ。
嬉しいですね。
最初は「INNFRAの実験で必要に迫られて…」でしたけど、標高800mほどのところで自然に囲まれながら暮らしているうちに、「これが本当にもっと山の奥地だったらどうだろう」「これまでの自分が想像し得なかった、どんな暮らしができるんだろう」というふうに可能性が広がって。ただインフラを作りたいというだけじゃなく、暮らしや体験の意味でたくさんのこと気づかせてもらった。それは自分の人生にとってもすごく大きなことだったと思います。
都市部の暮らしだけでは感じ得ないことがあった、と。
僕もそうだったんですけど、スタートアップの初期って「どのテーマに自分の人生を賭けるべきか」と悩むフェーズがあるんです。そこで半ば自分探し的に課題を見つけるためにも、こういう環境に身を投じられたことがすごくよかった。「この環境もこれで素晴らしいけれど、もっともっとよくできる」という観測のほか、地元の方とコミュニケーションを取るうちに東京に暮らしているだけでは見えなかったものが見えてきました。そういうのって、いくらネットでリサーチしても降りてはこないんです。
なるほど。
スタートアップを生み出す前夜のような、ここが起業の一番重要なポイントだと僕は思っているんですけど、そこでこそ地方に飛び込むというのはおすすめ。そうすると、「自分ごと」の課題を見つけられる。そういう意味でも僕は幸運でした。
「人のつながり」の価値
今、全国的にスタートアップ支援の機運が高まっている中で、山梨のユニークなところを改めて挙げてもらうとしたらどんなところだと思います?
「人のつながりがもたらしてくれるものの大きさ」じゃないですかね。課題を解像度高く認識するというのは、コミュニケーションを重ねないと難しい。課題があることが分かったとしても、そこからもう一歩踏み込んで入り込んでいかないと具体的な取り組みに落ちていかなかったり、技術開発やビジネスが進んでいかなかったりするケースも結構あると思っていて。
僕らは今まで、県の職員さんがわりとパーソナルに支援してくださっていたと思うんですが、そういうことが有機的な“場”としてできていくことで、僕らみたいな仕掛けができるようになるスタートアップってたくさんいると思う。
今まさに作っている支援拠点はそういう “場”にしたいと思っているんです。スタートアップが飛び込める先であり、そこに地元企業や行政もいて、みんなで一緒にやっていけるような拠点にしたいと。

民間企業さんや産業界との繋がりを自然に持てるようになる拠点。単独で乗り込んできたスタートアップにとって、すごく価値があるものになりますね。その場所があるだけで、ビジネスのスピードも広がり方も違うと思う。オンライン主流の時代であっても、オフラインを含めてコミュニケーションを取っていくことは地域に根付いていく上で欠かせないと思っていて。そういう機会を自然に得られるのであれば、拠点としての大きな魅力になると思います。
自然に、というのがキーワードですよね。この拠点を作ることによって自然とつながりが生まれるという状況を作ることができれば、それは我々の負荷軽減としても有難い。人的リソース、ギリギリですから(笑)。
笑
最後に、INNFRAさんは今後の展開をどのように考えていますか?
山梨って日本の中でもずば抜けた観光のポテンシャルがあるし、あとは災害対策という点で課題に直面している市町村もある。僕らがモデルを作る地としてベストだと思っているんです。だから、それぞれのマーケットをまず山梨でトライして作り上げ、「山梨モデル」として、広域的に広げていけることが理想ですね。
なるほど。
地域・土地・環境に向き合うというのは、インフラをテーマに掲げている以上は欠かせない部分であり、それを実践したのが八ヶ岳ラボでの成功体験でもある。だから、アプローチとプロセス自体は変えず、ここで作り上げたものを「山梨発です」と展開していく。それは、これだけの支援体制の中でやらせてもらっている僕らの責務のようにも感じています。
嬉しいですね。自治体として支援する側からすると、支援先のスタートアップが「県外に出ていく」というお話は素直に喜べないのが一般的です。でも、山梨県は、県外に出ていくことを完全に応援できるんです。なぜなら「出資」という手法を使っているから。「どんどん外にも出ていってください!」と背中を押して、成長を心から喜ぶことができるんです。
有難いお話です。そしてやはり、自治体がそこまでリスクを取るというのを聞いたことがないですね(笑)




